
三大香木のひとつであるクチナシ(梔子)は、秋の金木犀・春の沈丁花と並んでとても良い香りを漂わせる美しい花です。
梅雨どきに白い可憐な花を咲かせるクチナシは、その甘い香りからケープジャスミンとも呼ばれています。
芳香は強く、花の時期になると姿を見るよりも先に香りで存在に気付けるほどです。
白いビロードのようなやわらかさのある花びらや、つやがあって常緑の葉が魅力のクチナシ。
冬でも葉が落ちないので、生垣やボーダーガーデンにもピッタリの植物です。
生垣として使用されるだけでもなく、果実は生薬や着色料としても使われています。
今回はそんなクチナシの花言葉や育て方を詳しくご紹介します。
クチナシ(梔子)の基本情報
| 学名 | Gardenia jasminoides |
|---|---|
| 英名 | cape jasmine・common gardenia |
| 科名 | アカネ科 |
| 属名 | クチナシ属 |
| 原産地 | 日本西部・中国南部・台湾・インドシナ |
クチナシ(梔子)の特徴
クチナシ(梔子)の名前の由来
クチナシ(梔子)の名前の由来は、黄色が混ざった赤褐色の実が熟しても割れない、つまり口が開かないという特徴から連想されました。
将棋や囲碁の盤の脚はクチナシの実をかたどっています。勝負に口をはさむな、という言葉遊びからクチナシの実を模して昔から作られてきました。
クチナシ(梔子)の活用方法
クチナシ(梔子)は花を観賞することはもちろん、果実がさまざまな用途に使用されていることでも知られています。
果実の用途とは食品や繊維の色素、生薬などです。
よく知られているところでは黄色の色素として、たくあんや栗きんとんなどに使用されています。
また、発酵させると青色に変化するため青色の色素にもなります。
中国ではくちなしの実を山梔子(さんしし・やまけし)と呼び、乾燥させたものが漢方薬として用いられています。
クチナシ(梔子)は庭木にもぴったり
クチナシ(梔子)はそれほど樹高が高くならないので、庭のアクセントや花壇などのボーダーにもぴったりです。
常緑の葉も楕円形でつやがあって花の季節以外でも楽しめます。
クチナシ(梔子)の花言葉
クチナシ(梔子)には、花言葉もポジティブなものが選ばれています。
「優雅」や「洗練」などの花言葉は、クチナシ(梔子)の純白の花びらからつけられました。
「沈黙」は前述したように熟した実が割れないことから連想されました。
「喜びを運ぶ」はクチナシの甘い香りから選ばれた言葉です。
「私は幸せです」という花言葉は、アメリカでダンスパーティに誘うときにクチナシの花を渡していた逸話からつけられました。
クチナシ(梔子)の種類
クチナシ(梔子)は一重で6枚の花びらをつけるのが一般的です。
しかし、品種改良によって八重の花びらをつけるものも生み出されてきました。
別名のガーデニアは主にこの八重咲のクチナシを指したものです。
アメリカの植物学者の名前が由来となっています。
ガーデニアは実をつけませんが、通常の一重のクチナシは秋に赤褐色の実をつけます。
それ以外にも、いくつかの変種が存在しますのでご紹介します。
ヤエクチナシ
八重咲の園芸品種です。花が大きいので、庭木のシンボルツリーや鉢花として楽しまれます。
雄しべが花弁に変化してしまっているため結実しません。
庭木には原種よりもヤエクチナシが使用されることが多いです。
ガーデニア(オオヤエクチナシ)とも呼ばれます。
ヒメクチナシ
花や葉、樹高など全体的に原種のクチナシやガーデニアより一回り小さい品種です。
樹高も30cmから40㎝程度でボーダーガーデンにぴったりの品種となっています。
クチナシ同様香りは高く、植え込みに使用されることが多いです。
コクチナシ
樹高が低く、枝が地面を這うように、横に伸び広がります。落葉樹の根締めに向いています。
一重咲き・八重咲き両方があり、3㎝くらいの控えめな大きさの花を咲かせます。
香りも他の品種と比較すると控え目です。
マルバクチナシ
原種のクチナシの葉は長い楕円形ですが、マルバクチナシの葉は丸みがかったかわいらしい形の葉です。
ゴールドマジック
花の色が白からクリーム色、黄色へと変化していく珍しい品種です。
フイリクチナシ
葉にクリーム色の斑が入るのが特徴です。盆栽としても愛されています。
クチナシ(梔子)の栽培・育て方
クチナシ(梔子)は耐暑性と耐寒性がある樹木なので、庭植えにしても育てやすいのが特徴です。
耐寒性はありますが、それほど強くないので日当たりの良い場所に植え付けましょう。
またクチナシは株が大きくなってしまうと、根付きにくくなります。
植え替えには不向きなので、地植えの場合には、場所を決めてから行いましょう。
乾燥にはあまり強くないので、根元に腐葉土やウッドチップを敷いて対策するのも効果的です。
水切れを起こさないように、保水性の高い用土を選ぶのがポイントです。
乾燥に気を付けていれば、肥料や剪定もそれほど必要なく育てやすい植物といえるでしょう。
クチナシ(梔子)の育て方情報
| 分類・形態 | 庭木・花木・低木 |
|---|---|
| 草丈・樹高 | 1~2m |
| 開花の時期 | 6月~7月 |
| 花色 | 白 |
| 耐寒性 | やや弱い |
| 耐暑性 | 強い |
| 特性・用途 | 常緑性・香りがある・生薬・食品添加物(色素)・染料 |
| 栽培難易度 | 普通 |
栽培スケジュール
| 植え付け | 3~4月 |
|---|---|
| 植え替え | 3~5月 |
| 剪定 | 5月~7月・9月 |
| 肥料 | 1月~3月・7月 |
| 開花 | 6~7月 |
| 収穫 | 11月~12月 |
クチナシ(梔子)の栽培に必要な準備・環境
日当たり・置き場所
クチナシは暑さに強く、寒さと乾燥に弱い特性があります。
耐陰性があるので、半日蔭での栽培がおすすめですが、日にあたる時間が少なすぎると花が付きにくくなります。
乾燥を避けるために、西向きの場所は避けましょう。日当たりのよい場所へ地植えする場合、マルチングをして乾燥を防ぐのも効果的です。
水はけを良くするために盛り土をするのもおすすめです。東北・北陸以北では地植えは避けて鉢植えで管理し、温室や室内で冬越ししましょう。
水やり
乾燥に弱いので水を切らさないように注意が必要です。
特に鉢植えは乾燥に気を付け、表土が乾いてきたらすぐにたっぷり水やりをしましょう。
鉢植えの場合、冬場でも水やりは必要です。春から秋は朝と夕方、土の表面が乾いていればたっぷりと与えましょう。
肥料
たくさんの肥料を必要とはしませんので、冬場と夏の開花後に有機性の肥料や油粕を与えましょう。
開花直後に1度だけ肥料を与えるのでも、問題ありません。夏以降に施肥すると枝ばかり伸びて花芽が付きにくくなるので注意しましょう。
用土
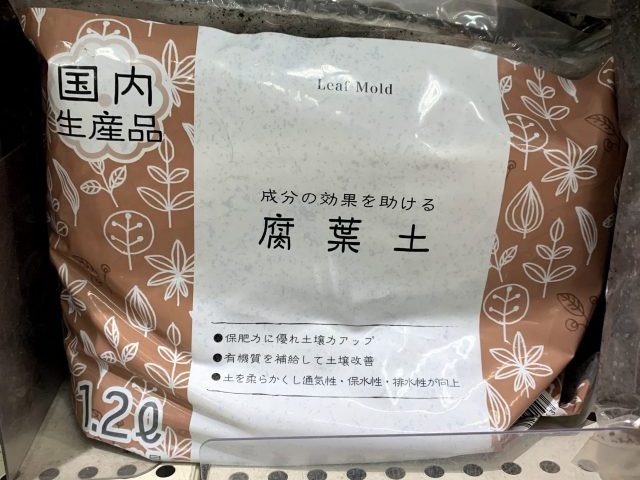
腐食性があり、水持ちと通気性のよい土を好みます。黒土に腐葉土を混ぜたものを使用しましょう。
クチナシ(梔子)を育てるときのポイント
クチナシは苗から育てるのが一般的です。寒さに弱いので寒冷地では地植えに向きません。
霜があたる可能性がある地域では鉢植えにし、冬季は日当たりのよい場所に移動しましょう。
選び方
葉が黄色くなっているものは避けましょう。葉がよく茂っているものを選びます。
植え付け・植え替え
根鉢の2~3倍の穴を掘ります。鉢植えの場合は根鉢よりひとまわり大きい鉢を選びましょう。
土には堆肥や腐葉土を混ぜ込み、水持ち・水はけのよい土にします。植え付け後は根がなじむようにしっかり水やりをしましょう。
鉢植えの場合は、数年に一度、ひとまわり大きめの鉢に植え替えるのがおすすめです。
庭植えの場合は、西向きの場所を避け、腐葉土や黒土を混ぜ込んだ用土に少し盛り土をして植え付けます。
地植えの場合は植え替えの必要はありません。
剪定
花が咲き終わった直後に剪定をおこないましょう。夏と秋の2回行うと、風通しがよくなります。
枝が込み合っている部分を切り風通しを良くします。
秋の剪定では、翌年の花芽がついてしまっているので強い剪定は避け、込み入った枝や伸びすぎた枝をカットする程度にとどめましょう。
根元付近から出ている枝は、花付きが悪いので剪定をしておきましょう。
鉢替え
根詰まりを防ぐため、2~3年に1度鉢替えをします。根についた古い土をきれいに落とし長く伸びた根は切り詰め、新しい土に植え替えます。
3月から5月におこないましょう。
ふやし方
挿し木で増やせます。5~7月ごろに新しい枝を切り、半分くらいまで葉を摘み取り、半日程度水揚げします。
その後に、しっかり湿らせた赤玉土か挿し木用の土に挿しておきます。
芽が出るまでは、半日蔭の場所で管理して水切れを起こさないように注意します。
1ヵ月ほど水を切らさないように日陰で管理すると発根するので植え付けをしましょう。
植え付けは秋か春に行います。コクチナシは根が横に這うようにして増えていくので、株分けでも増やすことができます。
収穫
11~12月ごろに収穫します。実は乾燥させると長期保存ができます。
気を付けるべき病気・害虫
病気
さび病、裏黒点円星病、褐色円星病、すす病などにご注意ください。
いずれも風通しが悪いと発生し、樹勢を弱らせてしまいます。
剪定で風通しを確保しましょう。
害虫
オオスカシバ、アブラムシ、カイガラムシにご注意ください。
オオスカシバという蛾の幼虫はクチナシが大好物で、放っておくと葉が食べつくされてしまいます。
春から秋にかけて葉の裏に1、2ミリの透明な卵を産み付けるので、見つけたら処分しましょう。
他にも葉に虫食いの穴を見つけたときや緑色のアオムシのような幼虫がついているときにも見つけ次第、駆除します。
予防のために薬剤を使うのも効果的です。
殺虫剤・殺菌剤
オオスカシバの予防にはオルトラン粒剤が効果的です。
また、幼虫はオルトラン水和剤やスミチオン乳剤で除虫できます。
殺菌剤はベニカ系の薬剤が効果的です。
