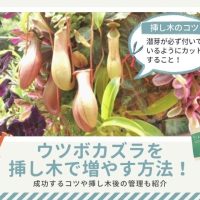白い粉が植物の葉に降りかかったように、まだらに変色しているのを見たことがありますか?
うどんこ病は、草花や野菜、庭木の葉などに多く見られます。
果樹や庭木などの樹木、トマトやキュウリなどの野菜や果実などにもみられる病気です。
うどんこ病はなにが原因で起きるのか、その対策と予防法など、植物を育てるためのポイントを紹介します。
うどんこ病とは?
うどんこ病は、さまざまな植物の葉に多く発生します。
初めのうちは、葉が白っぽくなっているのを気にとめないでいると、病気が進行してしまうかも。
葉にうっすらとうどん粉をふりかけたような斑点ができ、しだいに葉の全面に白く広がります。
病気が進行すると、葉が黄色く枯れてくることもあります。
葉が枯れると光合成ができず、茎が枯れてしまえば、その先は全部枯れてしまいます。
葉だけではなく、野菜や果物の実を台無しにしたり、近くに植えた植物にも感染することがありますので、早めの対策が必要です。
白い粉の正体は?
白い粉の正体は、糸状菌というカビの一種です。植物によって、原因となるカビの種類が少しだけ異なります。
春から秋にかけてが、うどんこ病が最も発生しやすい季節です。
カビというと高温多湿な環境が原因と思いがちですが、うどんこ病の原因となる菌は、乾燥した環境にも耐性があります。
うどんこ病のカビはどこから来る?
うどんこ病の糸状菌は、ふだんは土壌の中に生息しています。
冬になって、発病した植物の症状が見られなくなっても、翌年にはまた再発することが多く、見つけたら対策をとることが肝心です。
うどんこ病にかかりやすい植物
うどんこ病は、ほとんどの植物に見られる病気といってよいでしょう。
野菜・果実
きゅうり、スイカ、カボチャ、メロンなどのウリ科の野菜、トマト、ナスなどのナス科植物、イチゴなども被害にあいやすいです。
蕾やヘタにまで広がることがあります。
特に初夏に葉を増やし、光合成をしながら蔓を伸ばして成長していくきゅうりやスイカなどのウリ科の野菜では注意が必要。
葉が枯れて光合成ができなくなると、成長が妨げられ、収穫にも影響します。
草花・ハーブ
シクラメン、ベゴニア、カトレア、パンジー、クレマチス、クリスマスローズなどの観賞用の草花にもうどんこ病の被害が多く見られます。
ローズマリー、ラベンダー、ミント、ディル、チャイブ、バジル、カモミールなどのハーブ類もうどんこ病にかかりやすいです。
害虫を寄せつけにくいといわれるマリーゴールドも、被害にあうことが知られています。
花木・果樹
ハナミズキ、あじさい、ライラックなどの花木や、ブドウや柿、ブルーベリー、ジューンベリーなどの果樹も被害にあってしまいます。
バラも、うどんこ病にかかりやすく、黒点病と並んでバラの大敵です。
葉が白くまだらに枯れるばかりでなく、広がると葉がちぢれ、落葉するなどの被害が見られます。
蕾に菌が繁殖すると、楽しみにしていた花が開花しなくなることもあります。
観葉植物・多肉植物
意外なところでは、サボテン、その他の多肉植物にも、うどんこ病のカビは感染します。
パキラ、ガジュマル、コーヒーの木などの観葉植物も同様に病気にかかります。
葉が白く変色していないか、水やりの際などに気をつけるとよいでしょう。
うどんこ病になったらどうする?
植物がうどんこ病にやられて、葉が枯れてきたり、白い斑点が目立つようになったら、まずはカビの繁殖をストップさせましょう。
そうしないと、被害が広がってしまいます。
近くの植物に移ることがあるのは、カビが風に飛ばされて付着するせいです。
病気になった枝葉は剪定をして、処分はきちんと!
うどんこ病にかかった葉や、被害の目立つ枝は、剪定をして処分しましょう。
うっかり忘れがちですが、剪定した枝葉は、農家では焼却処分することもあります。
一般にはカビが飛び散らないように片づけて、燃えるゴミとして処分することです。
原因となるカビは、土壌を住みかに繁殖する糸状菌のため、枯れて落ちた葉にも付着し、消えたかに見えても、再発生することがあります。
うどんこ病になった植物の周囲に落ちている枝葉を、念のため処分することも大切です。
うどんこ病になりにくい栽培環境
うどんこ病の原因菌であるカビは、初夏から晩秋にかけて特に繁殖します。
ただし、土壌で生活するので、冬に消えるわけではありません。
栽培環境を整えるだけでも、うどんこ病の原因はかなり取り除けます。
植物の被害を予防するためには、カビが繁殖しにくい環境を作ることがポイントです。
風通しをよくし、密植を避ける
風通しが悪いと、カビには絶好の環境となります。
植物の種類によって、うどんこ病のカビは種類が異なります。
同じ植物を広い範囲に植えていると、病気にかかったときには、すぐに広がってしまいます。
いろいろな植物を植えたり、草花や樹木の枝が密集しすぎないように、間隔をとるなどして、風通しがよくなるようにしましょう。
適度に枝を剪定することも大切です。
日当たりは適度に
日当たりもよいほうが、カビは繁殖しにくいため、植えられた植物の種類にもよりますが、適度に日光があたるようにしたいものです。
肥料のバランスにも注意
チッソ成分が過多で、カリウムが不足していると、うどんこ病が広がる原因となります。リンと並んで、チッソ、カリウムは肥料の3大成分です。
肥料の偏りにも注意しましょう。
水やりのポイント
うどんこ病のカビは、湿っていても、乾燥していても、どちらにも強いことが知られています。
乾燥しすぎていると、土と一緒にカビが飛散しやすく、逆に湿りすぎていると、別の病気の原因にもなることがあります。
植物に合った適度な水やりを心がけていれば、問題はありません。
泥のはね返りが、感染を引き起こすこともあります。水やりをするときは、泥が植物にかからないように気をつけましょう。
畑での野菜の栽培であれば、ビニールなどで地表を覆うマルチングも有効です。
身近にある酢や重曹でうどんこ病を予防できる!
実は、家のキッチンにある身近なもので、うどんこ病の予防が簡単にできることが知られています。
それが、酢を水で薄めたスプレーと、重曹を水で薄めたスプレーです。
酢は酸性、重曹はアルカリ性と、逆の性質をもちますが、殺菌作用があるという点では同じです。
アブラムシ、ハダニ、コナジラミなどの害虫を、寄せつけない働きもあります。
ただし、自分で作る場合には、スプレー液が濃すぎると、植物自体にもダメージを与えてしまいます。
スプレーの作り方は次の通りです。
酢スプレーの作りかた
酢は、水で1対15くらいの割合に薄めます。
普通の食用酢3mlに対し、水を45mlくらいを加えればよいでしょう。
市販の食用酢を使った園芸用の防虫剤や、木酢液でも同じ効果が得られます。
重曹スプレーの作りかた
重曹は、水で1000倍くらいに薄めます。重曹1gの量に対し、水1リットルを加えます。
スプレーの使いかた
うどんこ病にかかったばかりの植物では、酢や重曹を使ったスプレーを、週に一度くらいかけるだけで、自然治癒してしまうこともあります。
アルカリ性土壌を好むブドウには、重曹の方がよいでしょう。
重曹を使ったうどんこ病に効く薬剤も市販されています。
逆に酸性土壌を好むブルーベリーには、酢の方がよいといえるでしょう。
被害が葉の表面にとどまる初期の段階では、特に効果を発揮するでしょう。
また、うどんこ病が発生しやすい初夏になったら、防虫もかねてスプレーを使えば、予防効果も期待できます。
うどんこ病の防除に効果のある薬剤
- 葉の多くが白い粉にやられている
- 黄色く枯れてきたといった
上記のように症状が進行していたら、うどんこ病の防除に効果のある市販の薬剤を使うことも考えなければなりません。
薬剤の選び方と使用上の注意
うどんこ病に効く薬剤は、殺菌作用のある様々な製品が販売されています。
病気にかかりやすいバラ用の薬剤や、イチゴ用、野菜用のもの、汎用的に効果を発揮する他の病気や、害虫にも効く薬剤など、各種あります。
たとえば野菜やイチゴなど食用になる植物には食品や医薬品にも使用される炭酸水素カリウムを主成分とした薬剤などがおすすめです。
安全性にも配慮され、そのまま肥料にもなる製品もあります。
薬剤の成分は、適合する植物の種類などは各社の製品の販売サイトや、店頭で手にする商品にも記載されています。
薬剤の使用にあたっては、用法や使用量などを守り、説明をよく読んで使うようにしましょう。
まとめ
うどんこ病の被害やその原因、家庭でもできる予防方法や、薬剤の紹介などをしてきましたが、早期に発見して対処することが大切です。
もともとは土壌に住んでいる菌が病気の元なので、必要以上に怖がる必要はありません。ふだんから植物の表情の変化にも気をつけて。
こまめに世話をしていれば、元気に復活させることも難しくはありません。