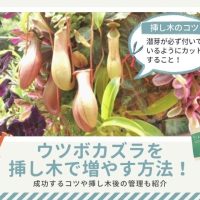カイガラムシとは花や木などの植物に寄生して栄養を吸い取ったり、植物の病気の原因になることもある害虫の一つです。
被害が広がれば大切に育てていた植物が枯れてしまう可能性もあります。
カイガラムシによる被害を広げないためにはできるだけ早く見つけて駆除すること、また予防策をとっておくことがとても大切なんです。
そこで今回はカイガラムシの生態や被害にあいやすい植物や、卵から成虫の段階に応じた駆除から予防方法まで詳しく解説します。
カイガラムシとは?
カイガラムシとはカメムシの仲間であり、その種類は国内だけでなんと400種類もいます。
種類によって表面が白い毛で覆われているもの、硬い表面に覆われているものまで姿はさまざま。
そして、脚が未発達で動かないものや反対に足が発達しており動くものまで、同じカイガラムシでも種類によって特徴が異なります。
カイガラムシによる被害
カイガラムシはほぼ全ての植物に発生し、寄生しては樹液や栄養を吸い取り最終的には枯らしてしまいます。
更に問題なのはカイガラムシによって植物の病気の原因となることであり、主な病気は以下の2つです。
すす病
すす病菌は植物のどこにでもいますが、カイガラムシの排泄物や分泌物をエサとしています。
カイガラムシが寄生して排泄することですす病菌が繁殖し、植物が黒いすすで覆われたようになってしまいます。
そのまま対処しなければ生育が遅れ、最終的には枯れてしまうのです。
こうやく病
カビの一種であるこうやく病菌はカイガラムシと共生しており、カイガラムシが寄生するとこうやく病も一緒に引き起こされます。
枝や幹の表面に、灰色や赤褐色のカビの膜が生え増殖すると植物の生育が衰えます。
また、病気とは別にカイガラムシの排泄物には糖分が含まれているため、その排泄物にアリやアブラムシが引き寄せられます。
一緒に多発することでも植物の生育が衰え枯れる原因になります。
カイガラムシの発生原因
カイガラムシは4月~10月頃に発生しますが、室内の植物の場合は年間とおして発生する可能性があります。
カイガラムシは小さいため、風にのって移動します。
外出時に衣類や持ち物につき部屋に持ち込んでしまったり、窓を開けていたら風とともに部屋に入ってきたりなどのパターンがあります。
また室内に侵入してきたカイガラムシは暗く風通しの悪い場所を好み繁殖するため、室内の環境が悪いと大繁殖を起こす可能性もあるんです。
幼虫と成虫では駆除方法が異なる
カイガラムシの幼虫は、殺虫剤をはじめ色んな対策が有効です。
成虫になると殺虫剤など液体が浸透しにくいため、駆除するには地道に落とすしかありません。
カイガラムシは成虫になると表面が貝殻のような殻やロウ物質に覆われるため薬剤が効きにくのです。
またカイガラムシは成虫でも小さく、幼虫と成虫を見分けることが難しいとされています。
ただし、幼虫が羽化する5月~8月は、殺虫剤などの薬剤が効きやすいためその時期に合わせて駆除することも有効です。
カイガラムシの被害にあいやすい植物
カイガラムシはどの花木でも発生する可能性がありますが、他の植物に比べ柑橘類などの果樹やバラ科の植物に発生しやすいです。
特にバラ・ウメ・サクラなどは要注意です。
また、室内の暗く風通しの悪い環境に置かれた観葉植物や、葉が密集している多肉植物などもカイガラムシが発生しやすいとされています。
カイガラムシの卵の駆除・予防方法
カイガラムシは5月~7月の頃に、植物の葉や葉裏などに小さく綿のような卵を産み付け孵化します。
カイガラムシの卵も成虫と同じように、殻に覆われていることから殺虫剤が効きにくいです。
卵が付いている枝を切り落とすか、卵を取り除く必要があります。
カイガラムシの卵を見つけたら、ティッシュで卵を落とすか、卵が付いた部分を切り落とすことで駆除することができます。
卵を落とす場合は、下に紙や袋を敷いておき卵が落ちても敷物ごと捨て取り残すことがないように注意しましょう。
予防策としては、葉や葉裏に卵を産み付けるため、葉や葉裏を観察し定期的にスプレーで葉水をして卵を洗い流しましょう。
カイガラムシの幼虫の駆除・予防方法
カイガラムシの幼虫は薬剤がよく効くので、卵や幼虫に比べ大量に発生しても比較的駆除しやすいです。
幼虫の時期にカイガラムシは確実に除去してしまいましょう。
おすすめの方法は以下の3つです。
殺虫剤を使用する
素早く簡単でかつ確実に駆除したい方は殺虫剤が一番おすすめです。
5月~8月頃に使用することで幼虫のカイガラムシを確実に駆除することができます。
カイガラムシエアゾールやベニカJスプレーなど、スプレー以外にも土に撒いて使うものあります。
牛乳を使用する
植物の影響も考えてできるだけ自然のものを使用したい方は牛乳を使い駆除する方法もあります。
方法は簡単で、牛乳を薄めてカイガラムシがいる部分にまきましょう。
牛乳は乾くと膜をはるので、その膜でカイガラムシの幼虫が窒息し駆除することができます。
また牛乳はカイガラムシだけでなくアブラムシにも有効です。
牛乳をまいた場合は、1~2日後に牛乳の膜を除去するために水で葉を洗い流しましょう。
木酢液を使用する
木酢液とは、木炭を作る時に生じる蒸留水を液体化して集めたものであり、高い殺菌・殺虫効果があります。
こちらも自然のものからできており、殺虫剤と違い安心して使うことができます。
使用する際はそのままでは、植物にも被害がでるため水で100倍に薄めたものをスプレーボトルにいれて吹きかけて使用します。
幼虫の予防方法としては、卵の時点で確実に除去することです。
しかし、数が多い場合は幼虫の方が薬液が効くので幼虫になってから除去する方が効果的な場合もあります。
また、外出した際や洗濯物などはお家に取り込む際はきちんとはたいてから家の中に入れましょう。
帰宅した際はできるだけ早く着替え衣類は洗濯機で洗うかコロコロを使うといいでしょう。
カイガラムシの成虫の駆除・予防方法
カイガラムシの成虫は殺虫剤など薬剤の効果が薄いため直接除去するしかありません。方法としては以下の2つです。
歯ブラシなどでこすり落とす
地道にこすって落としていく方法です。
歯ブラシなど硬い物を用いて落としていきますが、その時に植物を傷つけないように落としていきましょう。
取れたカイガラムシはティッシュなどに包んで確実に捨てて下さい。
また取りきれなかったカイガラムシを、お風呂や外などでシャワーなど水をあてて洗い流す方法もあります。
ただしあまりやり過ぎると植物の根腐れの原因にもなるので注意が必要です。
剪定する
もしカイガラムシが付いている場所が剪定可能な部位であった場合は、切り落とすことも有効です。
確実に除去でき、また植物が傷つく心配もないので、可能であれば剪定する方がいい場合もあります。
切り落とす際は、カイガラムシや卵がおちないように下に袋を広げて置き剪定しましょう。
ただし、剪定する際は芽を切り落としたりしないように、剪定しても大丈夫かどうか確認してから行ってくださいね。
カイガラムシの成虫の予防は、成虫になる前にしっかり駆除することです。
成虫すると駆除しにくくかつ卵を産み付ける可能性があり、除去後も再び発生しないか注意が必要となります。
カイガラムシの駆除をするときの注意点
カイガラムシを除去する際はカイガラムシの体液が付くことのなうように、マスクや手袋をして行いましょう。
そして除去後は早めに手を洗うことをおすすめします。
またカイガラムシを除去する際に着ていた服などは、カイガラムシが付着している可能性があります。
できるだけ早く着替えて洗濯しカイガラムシが家の中に残ることがないように注意してください。
更に、駆除した後のカイガラムシの死骸も確実に除去しましょう。
カイガラムシの死骸は放置するとそこから幼虫が生まれるため、せっかく除去したのにまたすぐに発生してしまいます。
そのため、除去する際は生きているものはもちろん死骸も取り残すことがないように注意しましょう。
まとめ
カイガラムシは5月~7月をピークにどの植物でも発生し、特に室内では年間通していつでも発生する場合があります。
被害を予防するためにも成虫になる前の幼虫の段階で駆除することが最も重要。
幼虫であれば殺虫剤だけでなく、牛乳など安全なものでも効果があるため、普段より葉や葉裏などにカイガラムシがいないか観察しましょう。
またカイガラムシは風に乗って移動するので、室内にカイガラムシを入れないことや繁殖しやすい環境を作らないことが大切です。
正しく予防して、早めに見つけることでカイガラムシの被害を減らすことができますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。