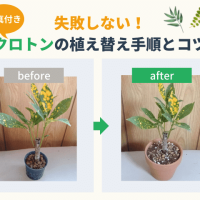ガーデニングをしていると、ネキリムシに悩まされたことがあるという人はたくさんいると思います。
せっかく大切にしている花や野菜が荒らされてしまうと悲しいですよね。
今回は、ネキリムシについて対策方法をご紹介します。
ネキリムシとはどんな害虫なのか?
そもそもネキリムシってどんな害虫なのでしょうか?
ネキリムシってどんな虫?

ネキリムシとは、夜に活動している夜蛾(ヤガ)のことを指しています。
- タマナヤガ
- カブラヤガ
- オオカブラヤガ
- センモンヤガ
など、複数の夜蛾を総称してネキリムシといいます。
見た目は、イモムシのようで子供が見つけると喜んだりするのですが、虫かごに入れられたらたまったものじゃありませんね。
大きさは、赤ちゃんのときで10~20ミリ程度ですが、成長してくると45ミリ程度まで大きくなります。
雑食性で、近くにある植物であれば何でも食べてしまうようです。
せっかく目が出た野菜も、こうしたネキリムシがいる限り立派な野菜に育つまでに食べられてしまうということです。
ネキリムシの発生時期は?
発生時期は、地域によって多少変わりますが5月から10月頃です。
寒い冬時期は、土の中に潜っていて夜に活動します。
ネキリムシは、夜に活動して花や野菜の茎や根元を食い荒らしているようです。
どんな野菜にネキリムシは付きやすい?
ネキリムシが付きやすいのは以下のような野菜です。
- 葉物野菜
キャベツ、ネギ、ホウレンソウ、白菜、小松菜 - 根菜
じゃがいも、大根、玉ねぎ、人参 - 果菜
トマト、ナス、きゅうり、インゲン
ネキリムシは雑食性なので基本的にさまざまな野菜に付きやすいです。
特に柔らかい葉や茎を好むため、野菜の苗を植えた直後はネキリムシの被害に十分注意しましょう。
農薬不使用のネキリムシ対策
ネキリムシの被害対策は、複数あります。
小さなお子さんやペットが庭で遊ぶご家庭などでは、「あまり農薬は使いたくない」ということもありますよね。
即効性はありませんが、農薬に頼らなくてもネキリムシ対策ができる方法は、いくつかあります。
農薬にたよらない対策方法
農薬にたよらない対策方法を紹介します。
- コーヒーの出がらしを活用
コーヒーの出がらしを、しっかり乾燥させて土に蒔く - 米ぬかを活用
米ぬかを植物の周りにまいて、ネキリムシに食べさせる - アルミホイルを活用
アルミホイルを植物の茎に巻いて、ネキリムシが食べられないようにする
どれも、ご家庭で簡単にできそうな対策ですね。
次の項目で、もう少し詳しくご紹介していきたいと思います。
ネキリムシ対策その①コーヒーの出がらし
自然成分で植物の成長を手助けするものを「自然農薬」といいますが、コーヒーの出がらしもその1つです。
実は、自然農薬という定義は曖昧なのですが、コーヒーはよく使われる自然農薬になります。
コーヒー土を作ろう!
コーヒー土という言葉をご存知でしょうか?
その言葉のままなのですが、コーヒーの出がらしと土を混ぜた土のことをコーヒー土といいます。
コーヒーの出がらしを直接蒔くと、水分を含んでいるのでカビが発生します。
水分を含んだコーヒーの出がらしは、植物の成長のための栄養どころか、反対に成長を妨げる成分を含んでいるともいわれています。
必ず、コーヒーの出がらしは1度しっかり乾燥させましょう。
しっかり乾燥させたら、土と混ぜてコーヒー土を作ります。
ポイントは、コーヒーの出がらしと土をよく混ぜて、しっかり乾燥させることです。
コーヒー土の作成手順を説明します。
![[ネキリムシ対策]コーヒー土の作成手順](https://gardenslibrary.com/wp-content/uploads/ce0a93a664ecdd6a521d9d8d21dae9ec.jpg)
- 土を作る入れ物を準備する
大きなプランターや鉢を用意するとコーヒー土を作りやすいです - 約3分の1程度の土を①で準備した入れ物に入れる
- コーヒーの出がらし(乾燥させたもの)ができあがったら、①で準備した入れ物に入れてよく混ぜる
- コーヒーの出がらし(乾燥させたもの)が追加でできたら、土と一緒に①に追加してよく混ぜる
コーヒーの出がらしと土の割合は適当で構いません - 熟成させる
目安の熟成期間は、1~2ヵ月
コーヒー土が完成したら、育てたい植物のまわりの土に混ぜ込んだり、蒔いたりしましょう。
コーヒー土にカビが発生したら
コーヒー土は、よく混ざっていないとカビが発生することがあります。
そんなときは、 カビもよく砕いて土に混ぜてしまうと良いそうです。
カビを発生させないポイントは、毎日混ぜて乾燥させることです。
そうすることで、徐々に堆肥化が進み、ふかふかした肥料用の土のようになります。
注意する点
コーヒー土には、化学農薬のように殺虫成分は含まれていません。
予防や忌避効果として試すことを前提 にしましょう。
コーヒー土は、植物によって合う合わないもあるので最初は少しずつ試しながら様子を見てください。
ネキリムシ対策その②米ぬか
2つ目は、米ぬかを使った駆除方法です、
ネキリムシは、米ぬかを食べるとお腹を壊して死んでしまうそうです。
また、米ぬかを食べることに夢中になるので、植物を食べなくなるともいわれています。
さっそく手順を確認してみましょう。
米ぬかを使った駆除手順

米ぬかを使った駆除手順を説明します。
- 米ぬかを準備する
- 植物の周りにたっぷり蒔く
これだけでOKです。
米ぬかを使った駆除方法も、とても簡単ですね。
注意する点
米ぬかを使って駆除をした場合、 米ぬかを好む他の虫がよってくる場合があります 。
米ぬかは肥料にもなるので、ネキリムシに困っているなら試す価値はありそうです。
また、米ぬかを食べて死んでしまったネキリムシを見るのが苦手な人は、注意が必要かもしれませんね。
ネキリムシ対策その③アルミホイル
最後は、アルミホイルを植物の根元に巻く方法です。
この方法は、先ほど紹介した2つより作業が手間かもしれませんが、こちらも効果的です。
アルミホイルを使った駆除手順

アルミホイルを使った駆除手順を説明します。
- アルミホイルを準備する
- 植物の茎にアルミホイルをしっかり巻く
1本1本丁寧に巻いていかないとだめなので、少し手間ですがアルミホイルを巻いて茎を保護することで、ネキリムシに食べられることはありません。
ただ、この方法はネキリムシ自体を駆除する対策にはなりません。
しかし、大切な植物を直接守るのに効果的な方法の1つです。
他の方法と併用してやってみるとより効果的かもしれません。
注意する点
特に注意する点はありませんが、畑の苗をアルミホイルで巻く場合は数が多くて大変な作業になるので、作業時間がかかるかもしれませんね。
また、慣れていない間は、茎を折らないように注意しましょう。
まとめ
科学農薬に頼らなくても、効果的な駆除方法があることをご説明しました。
身近なもので、大切な花や野菜を守ることができます。
ネキリムシに悩んでいるなら、早速試してみませんか?
子供と一緒に作業すると、楽しみながら花や野菜を守ることができそうですね。
もしも無農薬での対策がうまくいかない場合は、土壌表面や作物の株元にまくだけの簡単な「ネキリエース」を使用するのも初心者にはおすすめです。