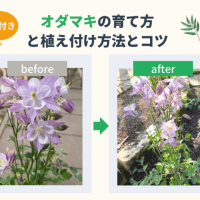白絹病は、植物の株元や周囲の土の表面に、白い絹糸のようなものがあらわれて、感染した植物をやがて枯らしてしまう病気です。
白絹病がどのような病気で、かかりやすい植物は?など、原因や、病気が起きやすい時期、予防方法などを解説します。
白絹病とは?
白絹病は、名前の通り、白い絹のようなカビが原因で起きる、草花や野菜、樹木など、多くの植物に発生する病気です。
白い絹糸のようなカビは、土の表面や株元に広がり、感染すると茎や葉にまで病気が感染し病気が進行すると茶色くなって枯れてしまいます。
しかもかかってしまうとまず治らないため、予防をしなければなりません。
茎や葉だけではなく、根やイモなども被害にあうことが知られています。
白い絹糸の正体は?
白絹病の原因は、ふだんは土壌の中に生息している糸状菌というカビの一種です。
菌が繁殖し成長すると菌核(きんかく)という粒のような褐色の塊となり、ここから白い糸状菌が繁殖します。
土の中にある菌核は、数年間は生存するため、いったん発生が見られなくなっても、翌年にまた再発することがあります。
菌は、酸素を取り込んで成長し、地表近くに絹糸のような白い菌が繁殖するため、見つけることは難しくはありません。
白絹病にかかりやすい植物
白絹病は、草花、野菜、花木や果樹などの樹木など、あらゆる植物に被害をもたらすことが知られています。
野菜・果実
- ネギ
- トマト
- ナス
- きゅうり
- ピーマン
- シシトウ
- オクラ
などの野菜や
- インゲン
- 大豆
- ラッカセイ
などの豆類、コンニャクなどのイモ類、スイカ、イチゴ、その他の野菜類はいずれも白絹病の被害にあいやすいものです。
植えた株元から白い絹のような、綿のようなカビが発生し、葉や茎を枯らしてしまいます。
茎にまで繁殖すると、白茶けた感じになって枯れてしまいます。
ネギに感染したときは、やはり葉の全体が、下の方から茶色く枯れて白いカビに覆われます。
草花・ハーブ・多肉植物
菊、リンドウ、ラン、ガーベラ、シュウメイギク、フジバカマ、ユキノシタ、その他の多くの草花にも、白絹病の被害が多く見られます。
ハーブ類や、多肉植物でも、白絹病にかかることが知られています。
花木・果樹
あじさい、沈丁花(ジンチョウゲ)、モミジなどの樹木でも、被害にあうことが知られています。
白絹病が発生しやすい原因(時期・環境)
白絹病は、6月から9月に多く発生する病気です。気温が摂氏25度になる頃になると発症します。
夏の暑い時期には特に発生が多く、気温が30度を超えると繁殖が早く、夏に植物に被害をもたらす病気です。
白絹病の見分け方
白絹病の見分け方は、白い粒があるかどうかを確認します。
土の中や根の間に白い粒のようなものがついていれば、白絹病の可能性が高いです。
白絹病はかかってしまったら治らない

植物が白絹病にやられたら、茎や葉が黄色く、やがて茶色く枯れてきてしまいます。
株元から、茎や根、葉にまで感染するため、治すのが難しく、予防することがなによりも大切です。
原因となるカビは、見つけたら取り除き菌がいた土壌も消毒するなど、他の植物に広がらないようにしましょう。
カビが繁殖する大元の土には、褐色の塊のような菌核ができます。
菌核を見つけて除去することも、忘れずに行いたいものです。
病斑のある葉を切り取り、剪定して風通しをよく
葉や茎が枯れてきたら早めに見つけて切り取りましょう。
白絹病であるとわかったら、枝ごと場合によってはあきらめて、株ごと剪定をしてしまいましょう。
剪定した枝葉は、カビが飛び散らないように片づけて、燃えるゴミとして処分します。
落ちている枝葉を掃除する
白絹病の原因となるカビは、枯れて落ちた葉や茎、根元にも付着しています。
カビのついている枝や葉、腐葉土ごと除去して捨てます。
周囲の土壌は消毒するなどの対処をしましょう。
病気の植物の周辺の土の消毒
白絹病のカビのいる土壌そのものは、土壌消毒剤などで消毒することもできます。
土壌消毒剤の使用にあたっては、説明をよく読んで使うようにしましょう。
表土の日光消毒にも効果があります。
日光消毒は、土をビニール袋に入れるか、シートなどの上に薄く敷いて、太陽の光に半日も当てれば効果的です。
土壌の天地返しは効果的
白絹病の原因菌は、白い糸状の菌と、そのもととなる菌核の茶色い塊です。菌核を見つけたらすぐに取り除いて処分すること。
除去した後でも、菌が残っていたら、酸素を取り込んでまた成長するかもしれません。
地表近くに白い菌が繁殖するため、土壌の天地返しをすることで、繁殖を抑えるのも効果的です。
薬剤の選び方と使用上の注意
白絹病にかかってしまったら、薬剤で直るということはありません。
ただ、周囲の植物に感染を広げないという意味では、予防の面からの意味はあります。
殺菌作用のある薬剤を使う場合には、用法や使用量などを守り、説明をよく読んで使いましょう。
白絹病を予防する方法
白絹病になりやすい環境は、カビが繁殖しやすい温度と、多湿、そして植物が弱りやすい条件が整ったときです。
風通しをよくし、密植を避ける
風通しが悪く、湿度が高いと、カビには絶好の環境となります。
間隔をあけて植えること、混みあった枝葉は選定することを心がけましょう。
日当たりは適度に
植物の種類にもよりますが、日なたにはカビは繁殖しにくいため、日当たり良好になる環境を作りましょう。
水やりは、やりすぎ、泥はねに注意
水をやりすぎたり、土壌の水はけが悪かったりすると、原因となるカビが繁殖する原因になります。
泥のはね返りが、感染を引き起こすこともあります。水やりをするときは、泥が植物にかからないように気をつけましょう。
酸素を取り込んで繁殖するため、ビニールなどで地表を覆うマルチングも有効です。
同じ植物の連作や、密植を避ける
同じ植物の連作を避けましょう。
草花や樹木の枝が密集しすぎて多湿にならないように、いろいろな植物を間隔をあけて植えるのも効果的です。
剪定をしたりして、風通しがよくなるようにしましょう。
雨にあたらない工夫も効果的
白絹病のカビは高温多湿を好みます。梅雨時などカビの繁殖の適温になります。
特にブドウなどは、梅雨時には、雨にあたらない工夫をすることも効果的です。
まとめ
白絹病の被害やその原因、予防方法などについて紹介してきましたが、症状が進むと治りません。
なによりも予防と、そして早期に発見して対処することが大切です。
土の中にある茶色い菌核の塊と、そこから繁殖する白い絹のようなカビを除去すること。
気をつけて世話をしながら、白絹病のカビが繁殖しにくい環境を整えることも無理なくできるでしょう。