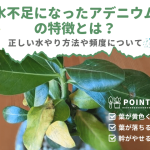- アデニウムがぶよぶよになる原因について理解できる
- アデニウムを腐らせない育て方が自分でできる
- アデニウムがぶよぶよになる原因と対処法がわかる
- ぶよぶよになる原因と対処法を理解し腐らせない育て方ができるようになる
アデニウムは、人気の塊根植物で、ふっくらと太った幹が最大の魅力。アデニウムの一番やっかいなトラブルは「アデニウムの幹がぶよぶよになってしまった」という失敗ではないでしょうか。一度ぶよぶよになると元には戻らず、ベテランでも枯らしてしまうことも…。どのような原因が考えられるのでしょうか。
こちらの記事では、アデニウムがぶよぶよになる原因と対処法や、腐らせない育て方を一挙紹介します。
アデニウムの幹がぶよぶよになる原因

アデニウムのすべすべだった幹肌が、なんだか変色してきたような?と気付いた時にはすでに遅し。触ってみると張りがなく、しわが寄りブヨブヨに…。初心者なら誰でも起こりうる失敗です。
アデニウムの幹や根っこがぶよぶよになるトラブルは、主に以下の5つの原因が考えられます。
- 最低気温
- 水切れ
- 水のやりすぎ
- 日照不足
- 風通しの悪さ
原因①最低気温が低すぎた
アデニウムは日光が好きなので、屋外で育てるのが好ましい植物です。しかし沖縄以北の地域では、屋外で冬越しすると低温障害で枯死することがあります。
「まだ秋だから」と油断していると、思いのほか気温が下がる日もあります。寒さに当たると幹にしわが寄り、幹肌の一部が変色、触るとブヨブヨとした触感に。しまった!と思っても後の祭りです。秋になったら天気予報をこまめにチェックし、最低気温が15℃を下回ったら室内に取り込みましょう。
原因②水切れによるしおれ
15℃以上の気温があるのに、アデニウムの幹が痩せてしわが寄っていたら、鉢から抜いて根腐れしていないかチェックしてください。もし根腐れしていなかったら、ただの水切れですので安心して育ててください。水を与えれば、ふっくら元に戻ります。もし季節が落葉期の冬なら、そのまま断水して休眠させます。春になり10℃以上になってから水やりを再開すれば、また葉っぱが展開してきます。
根腐れによるしおれ
アデニウムのぶよぶよの原因は根腐れかもしれません。アデニウムを鉢から抜いて根を見てみて、根っこが茶色や黒に溶けていたら根腐れしています。根腐れにはどんな原因があるのか、次で詳しく解説します。
原因③水のやりすぎによる根腐れ
アデニウムの鉢内が湿っていたら「水のやりすぎ」による根腐れかもしれません。育てている環境や、植え付けている用土、鉢の材質により、水やりの適量が異なるため、よく観察し、水やりの経験値を上げていきましょう。最初は用土に竹串などを挿して、湿っている土がついてくるか見てみると良いでしょう。
また、冬の休眠明けの水やりはごく少量から始めます。いきなりたくさん与えると根腐れすることも。休眠明け1ヶ月後から普通の水やりをしましょう。
原因④日照不足による根腐れ
一見、関係ないように思えるかもしれませんが、日当たりが悪くても根腐れは起こります。日に当たると根から水が吸い上げられ、光合成が活発になり、葉の気孔から呼吸しながら水分を蒸散。それがポンプの役割を果たし、また根から水を吸って光合成をして…を繰り返すのが正常な状態です。
しかし雨天続きや室内栽培などで十分な日光が与えられないと、光合成も緩慢になり水を吸わないので、根鉢の中にいつまでも古い水が残り、不衛生に…。それが根腐れの原因となってしまいます。
原因⑤風通しの悪さによる根腐れ

こちらも一見、根腐れとは無縁に思うかもしれませんが、風通しも重要なポイントです。アデニウムの原生地は乾燥した砂漠地帯で強い風が吹いているような環境です。自宅の栽培下でも、適度に風が吹いていると、葉の蒸散が促進され、根から水をよく吸い上げるようになります。閉め切った室内など、空気が流れていない場所では、鉢内で水が停滞し、根腐れの原因となる場合があるので気を付けましょう。
アデニウムのぶよぶよになった部分の取り除き方

「低温障害」や「根腐れ」により、幹がぶよぶよになったアデニウムを放っておくと、そのまま枯死することも…。ブヨブヨとした部分を切除すれば、枯れずに生き延びる可能性があります。どちらにせよ枯れるなら、ダメ元で緊急オペをしてみてはいかがでしょうか。
切除に必要な道具は
- よく切れるナイフ(カッターでも可)
- ベンレート水和剤(トップジンMペーストでも可)
- 清潔な鉢
- 清潔な無機質の用土
- 手袋
なお、緊急手術をしても必ずしも治るわけではなく、生き残るのは3割~5割程度かもしれません。患部の程度にもよりますが、底力のある株のみ生き残ることができるようです。
手順①鉢から抜いて用土を落とす

アデニウムの樹液が皮膚に付くとかぶれるので、ニトリル手袋などを装着して行います。ぶよぶよになったアデニウムを鉢からそっと抜き、用土を落とし、根腐れした根っこを取り除きましょう。不衛生な用土が残らないよう、残った根を優しく水洗いします。
手順②清潔なナイフで切除する
アデニウムのブヨブヨした幹を削り取るように切除します。傷んで変色した部分がすべてなくなるまで、深くえぐり取りましょう。ナイフは清潔なものを使用します。ウイルス病など媒介しないように、器具の消毒薬に浸けるか、バーナーなどで刃をあぶると良いでしょう。
手順③ベンレート水和剤を振りかける

治療効果と予防効果を兼ね備えた粉末の殺菌剤「ベンレート水和剤」を、切除した患部に振りかけます。アデニウムの幹からは樹液が出るので軽く拭いてから、水で希釈せずにそのまま粉をまぶして消毒します。ベンレートがなければ癒合剤でも可能です。
手順④清潔な鉢と用土で植え付ける
緊急オペが終わったら、新しい鉢と未使用の清潔な用土で植え付けます。用土は腐葉土や堆肥などの有機物が入っていない、砂系の無機質の用土のほうが安心です。植え付けたら1週間ほど水やりはせず、日陰で様子を見ます。以降、新根が出るまでは水やりは控えめに与えましょう。休眠期なら春までそのまま断水します。
アデニウムの幹をぶよぶよにしない育て方
アデニウムは、一度ぶよぶよにしてしまったら助からないことも多いので、最初から「幹をぶよぶよにしない育て方」を心掛けるようにしましょう。
アデニウムを腐らせない育て方は、前述したとおり、
- 寒さに当てない
- 日に良く当てる(真夏は薄く遮光)
- 水をやり過ぎない
- 風通し良くする
ことが大切です。
最低気温10℃を目安に、なるべく屋外の良く日の当たる場所で育成します。これらに注意して育てれば、幹をぶよぶよにせずに健康的に育てることができますよ。
まとめ
アデニウムがぶよぶよになる原因と対処法について解説しました。初心者のみならず、ベテランでも油断すれば幹をぶよぶよに腐らせてしまい、患部が深いと助からないことのほうが多いようです。簡単に治るものではないので、本記事をしっかり読んで、最初からぶよぶよにしないように心がけましょう。