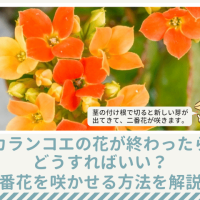梅雨など長雨の季節には、さまざまな植物の病気が発生しやすいものです。
べと病もその一つ、カビによる伝染病で、野菜のほか、草花や果樹などにも感染する、比較的よくみられる病気です。
発病後に防除するのが難しく、被害にあう前に予防することが大切です。
べと病がどのような病気で、どのような症状が出るのか?原因やかかりやすい植物と時期、予防方法などのポイントを紹介します。
べと病とは?
べと病は、きゅうりやネギなどの野菜のほか、草花や果樹などの葉におもに発生し、カビが原因で感染する伝染性の病気です。
感染すると、葉にすすけたような、ぼんやりした病斑ができ、植物の生育も悪くなる病気です。
植物の種類によって、原因となる菌は少し違い、症状も異なります。
病気が進行すると、病斑は褐色や黒に近い色に変色し、カビが繁殖して、植物を枯らしてしまいます。
いったん感染すると防除は難しく、なによりも予防を心がけましょう。
べと病の原因は?
べと病にかかると、植物の葉に、丸い小さな斑点ができます。べと病の原因は、糸状菌というカビの一種です。
葉に症状があらわれると、病気の葉は光合成ができなくなり、植物の生育に影響します。
べと病がさらに進行すると、葉が黄色く枯れて、落ちてしまうこともあります。
黒いカビは胞子によって増え、病斑を拡大させたり、近くにある植物にも感染することがありますので、早めの対策が必要です。
べと病にかかりやすい季節は?
べと病は、5月から9月、特にカビが繁殖しやすい梅雨の時期に、多く発生する病気です。
気温が摂氏15度から20度になる頃になると発症します。
真夏の高温のときには繁殖の勢いが弱まり、いったん収まるように見えますが、秋になって、また広がることもあります。
また、土壌で生活するので、冬に消えるわけではありません。
べと病の発生原因・伝染経路
べと病のカビはどこから来る?
べと病の糸状菌は、ふだんは土壌の中に生息しています。
感染した植物の葉に付着したカビから、胞子が風や雨で飛散し、別の葉や植物に侵入して伝染します。
水やりや雨の泥はねによっても、感染することが知られています。植えられた植物の株元や、地面に接している葉から感染することもあります。
冬になっても、菌がまだ潜んでいるため、翌年にはまた再発することがあります。
べと病にかかりやすい植物
草花
クリスマスローズ、ひまわり、アスター、ボタン、トルコギキョウなどの観賞用の草花にも、べと病の被害が多く見られます。
野菜
きゅうり、スイカ、カボチャ、メロンなどのウリ科の野菜や、ネギ、玉ねぎ、ニンニクなどは、被害にあいやすい植物です。
ダイコン、カブ、キャベツ、ブロッコリーなどのアブラナ科や、トマト、ナスなどのナス科植物、イチゴその他の多くの野菜にも感染します。
花木・果樹
バラなどの花木や、ブドウなどの果樹も、よく被害にあうことが知られています。
バラでは、葉に不定形の灰褐色の病斑ができ、茎や花梗にも発生します。
ブドウの場合には果実にも感染し、褐色に変色してカビが付着した状態になります。
べと病を予防する方法
べと病になりやすい環境は、カビが繁殖しやすい高温多湿の条件が整ったときです。
落ちている枝葉や残さ(残渣)を掃除する
べと病の原因となるカビは、土壌を住みかに繁殖し、枯れて落ちた葉や茎にも付着して生きていることがあります。
前年の枝葉など、べと病のカビが付着している可能性のある、植物の周囲に落ちている枝葉を掃除して、処分しておくことも大切です。
風通しをよくし、密植を避ける
風通しが悪く、湿度が高いと、カビには絶好の環境となります。間隔をあけて植えること、混みあった枝葉は選定することを心がけましょう。
日当たりは適度に
日なたにはカビは繁殖しにくくなるよう、日当たり良好になる環境を作りましょう。
肥料について注意点
肥料不足で株が衰弱している場合にも、べと病に感染しやすくなります。
逆にチッソ肥料が多すぎるときにも発生しやすいため、バランスに注意を。
水やりのポイント
水のやりすぎや、水はけの悪い土は、べと病の原因となるカビが繁殖する要因になります。
べと病のカビの繁殖は、胞子が風に飛ばされて他の植物にうつるほか、水やりの際の泥のはね返りが、感染をもたらすこともあります。
水やり時に、泥が植物にかからないように気をつけましょう。ビニールなどで地表を覆うマルチングも有効です。
雨にあたらない工夫も効果的
梅雨時などカビの繁殖の適温になり、雨が多い時期には、雨にあたらない工夫をすることも効果的です。
鉢植えであれば、季節によって置く場所を移動することもできるでしょう。
【きゅうり・玉ねぎ】植物別のべと病の症状
きゅうりがべと病にかかったら?
きゅうりなど、ウリ科の植物がべと病にかかると、葉には、葉脈どうしの間に黄色い斑紋ができます。
まくわうり、メロン、カボチャなどでも同様の症状があらわれます。
病気が進行すると、葉が茶色く枯れてしまいます。
このとき、葉の裏には黒っぽい色のカビが繁殖し、胞子が風や雨で周囲に飛散する原因となります。
胞子は、葉の気孔から侵入して伝染します。
玉ねぎがべと病にかかったら?
玉ねぎがべと病にかかると、細長い葉には不定形の黄色い斑紋ができます。病気が進行すると、下の方から茶色く枯れてしまいます。
ネギ、ニンニク、ワケギなど、同じ仲間の野菜にも同様の被害が広がります。
ブロッコリーがべと病にかかったら?
ブロッコリーがべと病にかかると、葉に黄褐色の病斑ができます。キャベツなどでも同様の症状がみられます。
葉の裏にはうっすらとカビが付着し、広がると食用部分の花蕾にも広がります。
花蕾には、黒っぽい病斑が生じ、切ってみると内部も黒っぽく変色している様子がみられます。
花蕾全体が変色したり、ひどいときには奇形になることもあります。
その他、多くのアブラナ科の野菜や、ウリ科野菜、ホウレンソウなどでも、感染した葉には、淡い黄色や黄褐色の病斑ができます。
症状が進行すると、大きな茶色っぽい病斑となって、葉が枯れてしまいます。
葉の裏はすす状のカビで覆われて、胞子で感染を広げる原因となります。
べと病になったらどうする?
同じ植物の密植を避ける
同じ植物を広い範囲に植えていると、病気がすぐに広がってしまいます。
草花や樹木の枝が密集しすぎないように、間隔をとるなどして、風通しがよくなるようにしましょう。
病斑のある葉を切り取り、剪定して風通しをよく
葉に病斑が出たら、早めに見つけて切り取ります。病斑のある葉が目立つ部分は、枝や茎ごと剪定をして処分することも大切です。
剪定した枝葉は、カビが飛び散らないように片づけて、燃えるゴミとして出しましょう。
薬剤の選び方と使用上の注意
べと病には薬剤もありますが、葉の多くがやられてしまい、枯れるほどに症状が進行していたら、薬で治すこともなかなか難しくなります。
早期に発見した場合には、殺菌作用のある薬剤を散布して、感染の拡大を抑えることはできるかもしれません。
べと病の防除のために、市販の薬剤を使う場合には、用法や使用量などを守り、説明をよく読んで使いましょう。
酢を水で薄めたものをスプレーすることでも、感染を抑える効果が得られます。
まとめ
べと病の被害やその原因、予防方法などについて紹介してきましたが、症状が進むとせっかくの収穫ができずに枯れてしまいます。
なによりも予防と、そして早期に発見して、感染が広がらないようにすることが大切です。
病気にかかりやすい季節になったら、カビが繁殖しにくい環境をこまめに整えてあげましょう。