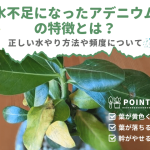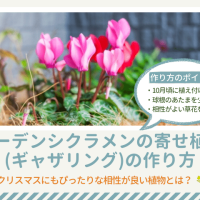さび病は、さまざまな植物の葉に病斑が出る病気で、植物によって症状の出方が異なります。
草花や野菜、樹木など、種類によりやや違う症状が出るため、見分けにくいかもしれません。
さび病がどのような病気で、かかりやすい植物は?早めに被害を抑えるための対策や、予防方法などのポイントを紹介します。
さび病とは?
さび病は、草花、野菜、樹木の多くに発生する、カビの一種である糸状菌が原因で、植物の葉に発症する病気です。
梅雨や秋の長雨など、春から秋にかけて多い病気で、気温が24度を超えると増殖が抑えられるため、真夏には発生が減少します。
植物の種類により症状が少し異なるものの、初期には葉に淡い色の斑点ができます。
感染が進行すると黄褐色のさびのように盛り上がった状態になります。
また症状によっては、葉が変形したりねじれたりする、植物の生育をさまたげる病気です。
さび病の原因は?
さび病の原因は、糸状菌というカビの一種です。さび病にかかると、植物の葉に、薄い色の斑点ができます。
感染初期に対処すれば、病気の進行を抑えることができる場合もあります。
カビの繁殖により病気が進行するため放置すると葉の裏表や茎にまで広がって、葉が変形したり、枯れてしまったりすることもあります。
葉についた病斑にはかびが繁殖し、胞子によって風や雨、水やりが原因で飛び散ると、さらに周囲に感染を広げてしまいます。
カビが好む多湿の状況を改善するなどして、予防をすることが大切です。
さび病にかかりやすい植物
さび病は、草花や野菜、樹木ほか、種類を問わず、ほとんどといってもいいくらいの、多くの植物に発生します。
草花
ユリ、菊、ベゴニアなどの草花や、なでしこなどの山野草にも、さび病の被害がみられます。
ミントなどのハーブ類も、さび病に感染します。
野菜
ネギ類は特に要注意です。ネギやニラ、玉ねぎ、ニンニクなど、ネギの仲間にはさび病が多く発生します。
カブ、ラディッシュ、小松菜などの葉物野菜、水菜、レタス、アスパラガスなどもさび病にかかります。
さらに、小麦、トウモロコシなどの穀物や、シソなどもさび病の被害にあうことが知られています。
ひどくなると、ほとんどの葉が枯れ、収穫を楽しむことも難しくなるでしょう。
果樹
ブドウやナシ、イチジク、びわ、桑などの果樹もさび病の被害を受けます。
樹木
バラ、ツツジ、あじさい、藤、キンモクセイなどの花木、クロマツ、山椒などの庭木も、さび病の被害を受けます。
芝
芝は、穀物のイネ科の植物で、やはりさび病に感染することが知られています。
さび病が発生しやすい時期・環境
さび病にかかりやすい時期
さび病は、4月~5月と、9月~10月頃、気温が摂氏15度から20度になる時期に発生します。
真夏の高温のときには繁殖の勢いが弱まり、いったんおさまるように見えますが、秋にまた要注意な季節となります。
梅雨や、秋の長雨シーズンには繁殖しやすい環境となりますので、注意が必要です。
さび病のカビが潜んでいる場所
さび病のカビは、ふだんは土壌の中に生息しているほか、枯れ枝や、弱った植物なども住みかとしています。
落ちている枝だけではなく、
- 剪定し忘れた枯れ枝
- 剪定した後の治癒していない大きな切り口
- ヒョロヒョロに伸びた徒長枝
などにも、カビが住み着いていることがあります。
植物がさび病になったときの対処法
植物がさび病にやられて、斑点が目立ち、葉が枯れてきたら、早めにカビの繁殖をストップさせましょう。
身近にある意外なもので、さび病の発生を抑えることができます。
重曹の散布
キッチンや掃除などで使うこともある重曹は、炭酸水素ナトリウムといいます。
水に溶かして薄めたアルカリ性の重曹の水溶液を、スプレーで散布すると、殺菌の効果が期待できます。
さび病にかかりやすい時期の、晴れているときに週に一度くらい散布してみるとよいでしょう。
重曹の水溶液は、重曹1gを1リットルの水に溶かしたくらいの濃度で作ります。
病斑のある葉を切り取り、剪定して風通しをよく
葉に病斑が出たら、早めに見つけて切り取りましょう。さび病にかかった葉が目立つ枝は、枝ごと剪定をして処分することも大切です。
剪定した枝葉は、カビが飛び散らないように片づけて、燃えるゴミとして出します。
薬剤の選び方と使用上の注意
さび病の被害がひどいときや、芝生のように広範囲にわたるときには、薬剤を散布する方法もあります。
殺菌作用のある薬剤として、市販の薬剤を使う場合には、用法や使用量などを守り、説明をよく読んで使いましょう。
特に野菜など食用の植物に使用する際には、成分や用量などをよく確かめましょう。
さび病を予防する方法
さび病になりやすい環境は、カビが繁殖しやすい温度と、多湿、そして植物が弱りやすい条件が整ったときです。
高温には比較的弱いため、真夏の暑い時には感染力は低くなります。
落ちている枝葉を掃除する
さび病の原因となるカビは、土壌を住みかにしています。
枯れて落ちた葉や果実にも付着しているため、消えたかに見えても、再発生することがあります。
前年の枝葉など、かび病のカビが付着している可能性のある、植物の周囲に落ちている枝葉を掃除して、処分しておくことも大切です。
風通しをよくし、密植を避けて、日当たり良好に
風通しが悪く、湿度が高いと、カビには絶好の環境となります。間隔をあけて植えること、混みあった枝葉は剪定することを心がけましょう。
日なたにはカビは繁殖しにくいため、日当たり良好になる環境を作りましょう。
水やりは泥はねに注意を
泥のはね返りが、感染を引き起こすこともあります。水やりをするときは、泥が植物にかからないように気をつけましょう。
水をやりすぎたり、土壌の水はけが悪かったりすると、原因となるカビが繁殖する原因になります。
ビニールなどで地表を覆うマルチングも有効です。
まとめ
さび病の被害やその原因、予防方法などについて紹介してきましたが、症状が進むと感染が広がります。
予防と、そして早期に発見して対処することが大切です。
枯れ枝や葉は除去すること、さび病になった部分は切り取って処分、重曹などを使って殺菌をして。
特に梅雨や長雨の季節になったら、カビが繁殖しにくい環境をこまめに整えてあげましょう。