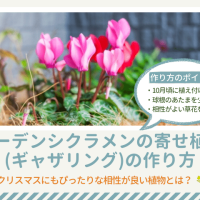地植えでも鉢植えでも、園芸愛好家には大人気のバラ。
バラの病気として、黒星病(黒点病)、うどんこ病、根頭がん腫(こんとうがんしゅ)病が知られています。
ほかにもさまざまな病気があり、バラを育てるのは難しいのでは、と思われるかもしれません。
それぞれの病気の特徴や対策を知っておくと、きっと役にたつでしょう。
そこで、注意したいバラの病気7つの、原因や症状、予防方法などについて紹介します。
注意したいバラの病気7つ
バラがかかりやすい病気として、黒星病(黒点病)、うどんこ病、根頭がん腫病が、特にやっかいなものとして知られています。
根頭がん腫病は細菌によって、黒星病、うどんこ病は糸状菌というカビによって、それぞれ引き起こされる病気です。
バラがかかる病気としてはほかにも、枝枯れ病、灰色かび病、べと病、さび病などが知られています。
いずれもカビが原因となるものです。
どの病気にかかった場合でも、葉が枯れたり、花が咲かなくなったり、生育に悪い影響が出ます。
症状や原因、対策法を知って、日ごろから注意することが大切です。
バラの病気7つの時期・原因・症状
黒星病(黒点病)
かかりやすい時期
5月から9月、特にカビが繁殖しやすい梅雨の時期に、多く発生する病気です。
症状
黒星病は、黒点病ともいい、葉に黒または褐色の丸い小さな斑点ができます。
黒い斑点がたくさんの葉に広がって、病斑は黒いカビが生えたような状態になり、ひどいときには多くの葉が枯れ落ちてしまいます。
原因と、かかりやすい環境
黒点病の原因は、カビ(糸状菌)の一種です。風通しが悪く、湿度が高いと、カビには絶好の環境となります。
黒いカビは胞子によって増え、近くにある植物にも感染することがありますので、早めの対策が必要です。
うどんこ病
かかりやすい時期
うどんこ病の原因であるカビは、初夏から晩秋にかけて特に繁殖します。
特にカビが繁殖しやすい梅雨の時期に、多く発生する病気です。
症状
葉にうっすらとうどん粉をふりかけたような斑点ができ、しだいに葉の全面に白く広がります。
病気が進行すると、葉が黄色く枯れてくることもあります。茎が枯れてしまえば、その先は全部枯れてしまいます。
原因と、かかりやすい環境
うどんこ病のカビは、ふだんは土壌の中に生息しています。近くの植物に移ることがあるのは、カビが風雨に飛ばされて付着するせいです。
根頭がん腫(こんとうがんしゅ)病
かかりやすい時期
春から秋にかけて、多く発生する病気です。
症状
バラの根や、地際の茎、接ぎ木した箇所などに、ごつごつしたコブができます。
コブは灰褐色から黒褐色で、乾いてざらついた状態となり、バラの生育に影響します。
ひどいときには株が枯れてしまうこともある病気です。
原因と、かかりやすい環境
病気の原因は細菌に感染したためで、細菌は傷口から侵入し、伝染によって広がります。
菌糸で成長する多細胞のカビとは異なり、細菌は単細胞で、自ら複製を作って増殖します。
病原となる細菌に感染し発病した株は、全体が感染している場合が多く、要注意です。
ただし原因菌自体は、土の中で普通に生息している、感染力はそれほど高くない細菌です。
枝枯れ病
かかりやすい時期
春から秋にかけて多いものの、ほぼ一年中、発生する病気です。
症状
おもに茎に褐色の病斑ができ、病斑はくぼんで、ぶつぶつの状態になります。
枝に病斑ができるのが特徴で、増殖すると枝が枯れてしまいます。
原因と、かかりやすい環境
カビに感染することが原因で、胞子が風や雨により飛来して付着し、傷から侵入するなどしてかかります。
カビが繁殖しやすい多湿な環境でかかりやすい病気です。
灰色かび病
かかりやすい時期
春から秋、4月から11月頃が、灰色かび病が発生しやすい季節です。
症状
病気にかかった葉や茎、花びらには、水に浸したような、灰色や灰褐色の斑点があらわれます。
病気が進行すると、灰色のカビに覆われた症状になり、植物全体が枯れてくることもあります。
原因と、かかりやすい環境
灰色かび病は、灰色のカビ(糸状菌)の一種が原因です。
多くのカビと同様に、多湿な環境がカビには好適な環境で、梅雨時や秋の長雨など、雨の続く時期に多く発生する病気です。
べと病
かかりやすい時期
べと病は、5月から9月、特にカビが繁殖しやすい梅雨の時期に、多く発生する病気です。
気温が摂氏15度から20度になる頃になると発症します。
症状
べと病にかかると、植物の葉に、丸い小さな斑点ができ、植物の生育に影響します。
べと病がさらに進行すると、葉にすすけたような、ぼんやりした病斑ができます。
病斑は褐色や黒に近い色に変色し、カビが繁殖して、植物を枯らしてしまいます。
原因と、かかりやすい環境
べと病の原因は、カビ(糸状菌)の一種です。黒いカビは胞子によって増え、近くにある植物にも感染することがあります。
さび病
かかりやすい時期
梅雨や秋の長雨など、春から秋にかけて多い病気で、気温が24度を超えると増殖が抑えられるため、真夏には発生が減少します。
症状
初期には葉に淡い色の斑点ができ、進行すると黄褐色のさびのように盛り上がった状態になります。
放置すると葉の裏表や茎にまで広がって、葉がゆがんで変形し、枯れてしまうこともあります。
原因と、かかりやすい環境
さび病の原因は、カビ(糸状菌)の一種です。
葉についた病斑にはかびが繁殖し、胞子によって風や雨、水やりが原因で飛び散ると、さらに周囲に感染を広げてしまいます。
バラが病気になったときの対処法
バラが病気にかかったら、よく観察し、どの病気なのかを見きわめて、早めの対処を心がけましょう。
カビが原因で起きるどの病気でも、病気になった時の対策には共通点があります。
一方で、その病気特有の対策が必要なものもあります。
そこで共通の対策と、その病気特有の対策とに分けて、それぞれのポイントを解説します。
根頭がん腫病にかかったら?
根頭がん腫病は、細菌によって引き起こされ、感染した植物の内部で倍々に増殖します。
株全体が感染していることが多いため、発病したバラは株ごとは抜き取って焼却、あるいは燃えるゴミとして出す必要があります。
根頭がん腫病が発生した土には、そのまま新しく植物を植えつけず、土壌の消毒、殺菌を行います。
土壌の殺菌には、熱湯消毒、日光消毒、土壌殺菌剤による消毒などがあります。
枝枯れ病、さび病にかかったら?
枝枯れ病にかかったバラの枝には、原因となるカビが生息しています。
さび病のカビも、土壌の中に生息しているほか、枯れ枝や、弱った植物なども住みかとしています。
- 剪定し忘れた枯れ枝
- 剪定した後の治癒していない大きな切り口
- ヒョロヒョロに伸びた徒長枝
などにも、カビが住み着いていることがあります。
これらの病気にかかったら、なによりもまず、枯れた枝を剪定します。
まだ枯れていない部分にまで広がっている可能性もあるので、少し広めの範囲まで剪定したほうがよいでしょう。
カビが原因の病気にかかったら?
病斑のある葉を切り取り、剪定して風通しをよく
黒点病・うどんこ病・灰色かび病・さび病・べと病など、葉に病斑が出たら、早めに見つけて切り取りましょう。
カビの病気にかかった葉が目立つ枝は、枝ごと剪定をして処分することも大切です。剪定した枝葉は、燃えるゴミとして処分すること!
薬剤で治すことは困難なことも、でも感染の拡大をストップ!
カビや細菌が原因で起きる病気には、殺菌のための薬剤もあります。
ただ、葉の多くがやられてしまい、枯れるほどに症状が進行していたら、薬で治すこともなかなか困難です。
ただし、感染初期には効果が期待できるほか、他の植物にカビがうつることを防止できます。
殺菌作用のある薬剤には、感染の拡大を抑える働きがあります。
予防のために、市販の薬剤を使う場合には、用法や使用量などを守り、説明をよく読んで使いましょう。
さび病などに効く重曹の散布、他の病気の感染の予防にも
植物がさび病にやられて、斑点が目立ち、葉が枯れてきたら、重曹の散布により、さび病の発生を抑えることができます。
キッチンや掃除などで使うこともある重曹(炭酸水素ナトリウム)の水溶液をスプレーで散布すると、殺菌の効果があらわれます。
重曹の水溶液は、重曹1gを1リットルの水に溶かした程度がよいでしょう。
黒点病・うどんこ病・灰色かび病・さび病・べと病など、カビが原因で起きる他の病気でも、感染の拡大を抑える殺菌作用があります。
この効果については次の予防方法で解説します。
バラの病気を予防する方法
カビが原因で起きるどの病気にも共通する、予防方法があります。
カビが原因の病気は、酢や重曹で予防できる!
家の台所にある身近なもので、黒点病・うどんこ病・灰色かび病・さび病・べと病などの予防が簡単にできることが知られています。
それが、酢を水で薄めたスプレーと、重曹を水で薄めたスプレーです。
酢スプレーの作りかた
酢は、水で1対15くらいの割合に薄めます。
普通の食用酢3mlに対し、水を45mlくらいを加えればよいでしょう。
市販の食用酢を使った園芸用の防虫剤や、木酢液でも同じ効果が得られます。
重曹スプレーの作りかた
重曹は、水で1000倍くらいに薄めます。重曹1gの量に対し、水1リットルを加えます。
スプレーの使いかた
病気にかかったばかりのバラの場合、酢や重曹のスプレーを週に一度かける程度で、自然治癒してしまうこともあります。
落ちている枝葉を掃除、燃えるゴミとして処分
病気の原因となるカビは、土壌を住みかに繁殖し、枯れて落ちた葉や果実にも付着します。
前年の枝葉など、黒点病のカビが付着している可能性のある植物の周囲に落ちている枝葉を掃除しましょう。
燃えるゴミとして処分しておくことも大切です。
風通しをよくし、密植を避け、日当たりは適度に
風通しが悪く、湿度が高いと、カビには絶好の環境となります。
間隔をあけて植えること、混みあった枝葉は剪定することを心がけましょう。
日なたにはカビは繁殖しにくいため、日当たり良好になる環境を作りましょう。
水やりは泥はねに注意を
水をやりすぎたり、土壌の水はけが悪かったりすると、原因となるカビが繁殖する原因になります。
泥のはね返りが、感染を引き起こすこともあります。水やりをするときは、泥が植物にかからないように気をつけましょう。
肥料切れはバランスよく
肥料のやり過ぎもいけませんが、肥料切れを防ぐこと。特に鉢植えの場合には注意が必要です。
バラの黒星病(黒点病)を予防する方法
特に、黒星病は、成長した葉がまずやられ、出たばかりの若い葉は、病気にかからないという特徴があります。
バラは、次々と若い葉が芽吹く元気な状態であれば、病気にはかかりにくくなります。
若い葉は、表面が保護皮膜によって保護されているため、原因となるカビの侵入を抑える働きがあるためです。
黒点病は、軒などの屋根のあるところや、温室などの降雨がかからない場所では、あまり発生しないこともわかっています。
梅雨時などカビの繁殖の適温になり、雨が多い時期には、雨にあたらない工夫をすることも効果的です。
鉢植えであれば、季節によって置く場所を移動することもできるでしょう。
バラの根頭がん腫病を予防する方法
はじめは鉢植えで
根頭がん腫病は、発症したら治らない、細菌感染による病気です。
苗が最初から感染していることもありますが、感染力や発症率は低い細菌でもあります。
一年間くらいは鉢で育ててみて、問題がなければ地植えしてもよいこととすれば、発生を予防できます。
地植えでは微生物が元気な環境を
地中には有用な微生物が無数に生息し、たい肥や有機肥料などで良質な土を作ることにより、がん腫病菌の繁殖を防ぐことができます。
予防薬
根頭がん腫病には、予防薬も市販されています。
バラ苗の植え付け、植え替えのときに薬剤の希釈液に浸し、根頭がん腫病の発病を予防するために使います。
まとめ
黒星病(黒点病)、うどんこ病、根頭がん腫病をはじめ、注意したいバラの病気7つについて紹介してきました。
しかし、バラがどの病気にかかるかは、事前にはそもそもわからないのです。でも、予防方法には共通する点がたくさんありますね。
カビが繁殖しにくい環境をこまめに整えるなど、予防方法はどれも簡単にできるものばかり。早期に発見して対処することが大切です。
きれいな花が咲くことを楽しみにしつつ、日ごろから気をつけたいものですね。