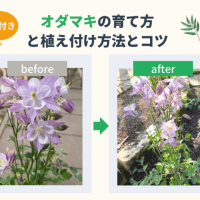テントウムシは可愛らしい姿と、アブラムシなどの害虫を食べてくれる益虫として良く知られている虫です。
そんなテントウムシにそっくりな姿をしているけど実は植物を食害する「テントウムシダマシ」という虫をご存じですか?
テントウムシだと思って放っておいたら、しばらくした後に植物がボロボロになってしまいます。
特に注意したいのが繁殖力の強さで見つけ次第早めに駆除すべき虫なんです。
そこで今回はテントウムシダマシの生態や植物への被害、駆除方法から予防方法まで紹介します。
テントウムシダマシとは
テントウムシダマシによる被害や発生する原因はどのようなものがあるのでしょうか?
テントウムシダマシは葉だけでなく果肉も食べる
テントウムシダマシは葉肉を中心に食害し、葉っぱの表皮と葉脈を残しバーコード状の食い跡が残ることが特徴です。
幼虫のは主に葉肉を食べますが、食欲旺盛であり植物の葉を食べつくすと葉だけでなく茎や果肉まで食べてしまいます。
また幼虫から成虫になると食害対象は葉や茎だけでなく花や果実まで食害してしまうのです。
そしてその食欲は幼虫や成虫が一匹でも生き延びると株全体がボロボロになるほどです。
最悪枯れてしまうこともあり被害が大きくなってしまいます。
テントウムシダマシの発生時期や原因
テントウムシダマシの発生時期は4~10月頃です。
越冬した成虫が春先にジャガイモなどの新芽を目当てに飛来しては、葉裏に黄色く小さい卵を30~50個ほど産み付けます。
そして孵化した幼虫が1ヵ月ほどで成虫となり6月以降に再び卵を産みつけるのです。
オオニジュウヤホシテントウなどの種類は年に1回の産卵ですが、ニジュウヤホシテントウなどの種類は年に2、3回産卵します。
そして1年を通し、幼虫から成虫へのサイクルを繰り返します。
またジャガイモの新芽などを食べつくした成虫は、その後ナスやウリ科などの植物を中心に食害します。
そのためジャガイモとナスやキュウリなどが近くに植えられているとテントウムシダマシが大繁殖する原因となることがあります。
テントウムシダマシの生態
テントウムシとテントウムシダマシとの違いや生態などを説明します。
テントウムシダマシの体は細かい毛で覆われている
テントウムシダマシとはテントウムシ科マダラテントウ亜科に属する昆虫の俗称です。
テントウムシ科に属する200種類ものテントウムシの中で約8割がこのテントウムシダマシと呼ばれている害虫なのです。
アブラムシを食べるテントウムシはナナホシテントウムシなど光沢のある赤い体に黒い斑点が特徴。
他にもキイロテントウムシなどのウドンコ病などの菌類を食べてくれる黄色やオレンジの色をしたものもいます。
一方でテントウムシダマシと呼ばれるテントウムシは羽の色が薄く鈍い色をしています。
体が細かい毛で覆われツヤのない体であることが特徴です。
テントウムシダマシの中でも気温14度以下の地域に生息するのがオニジュウヤホシテントウです。
それに対して、気温が14度よりも高い地域に生息しているのがニジュウヤホシテントウと呼ばれる種類。
テントウムシダマシの幼虫は体長約4mmほどのタワシのような形で、クリーム色の体にたくさんのトゲが生えたような姿をしています。
ナナホシテントウムシなど益虫であるテントウムシに比べテントウムシダマシの成虫は動きが鈍く簡単に手で捕まえることができます。
テントウムシの産卵数は他に比べてとても多い
テントウムシダマシを含めるテントウムシは繁殖力が強いという共通の特徴があります。
それはテントウムシ一匹が死ぬまでに産卵する数が他の虫に比べてとても多いからなのです。
植物に被害を与えないナナホシテントウも2ヵ月も産卵を続け1匹で2000個近い卵を産卵します。
テントウムシダマシはそれよりは少ないですが、産卵数は一匹に対して500~700個にもなると言われています。
産み付けられた卵が一気に孵化することで、最初は数匹だったテントウムシダマシが気づけば一気に大繁殖なんてこともあります。
テントウムシダマシが好む植物
最初に少し触れましたが、テントウムシダマシはジャガイモやナス科の野菜を好んで食害し、被害が多く見られます。
その他にはトマト、きゅうり、唐辛子、ピーマン、えだまめ、ゴボウ、白菜、ホオズキ、イヌホオズキなどの種類も食害します。
新芽を食べられることで株自体がだめになる、葉を食害されて光合成の効率が下がり発育の阻害や収穫量の低下につながる場合もあります。
テントウムシダマシの駆除方法
テントウムシダマシを見つけてしまった場合の駆除方法はさまざまなものがあります。
その中でも農薬を使う場合と農薬を使わない場合の駆除方法を紹介します。
テントウムシダマシを農薬を使い駆除する方法
テントウムシダマシが大量発生してしまった場合などはやはり農薬を使用した方が、即効性があり確実に駆除することができます。
テントウムシダマシに有効なスミチオン乳剤はナスやばれいしょに使用でき、収穫3日前まで使用することができます。
その他にも農薬は駆除したい植物が適応する農薬を確認してから選びましょう。
使用方法としては農薬を規定量に薄めて、1週間に2、3回を目安にテントウムシダマシのいる植物に散布してください。
テントウムシダマシを農薬を使わずに駆除する方法
テントウムシダマシを駆除するためには、植物全体と葉裏をよくチェックしてください。
特に卵は葉裏に産み付けられるため、葉裏から卵が見つかればすぐに駆除しましょう。
卵の段階で駆除できれば植物への被害も小さく済みます。卵から孵化した幼虫と成虫の駆除のポイントは以下の2つです。
幼虫がいる葉は葉ごと処分する
幼虫はとても小さく見つけづらいですが、基本集団行動をしているので葉裏に幼虫がびっしりついていることがあります。
取り残すことがないように葉ごと切り取って畑の外で処分するか、袋など密閉できるものに入れて処分するようにしましょう。
成虫を捕殺する際は下に敷物を
成虫は株元の込み入った葉の根本部分にいることが多く、根元付近の葉裏はよくチェックしましょう。
見つけることができたら動きは鈍いので手で捕殺することができます。
葉が込み入って手が入りにくい部分などは取り落とすこともあります。
下に紙やペットボトルをカットしたものなどを置いておくことで確実に駆除することが可能です。
テントウムシダマシの予防方法
テントウムシダマシの予防方法は以下の4つです。
- 幼虫や卵を発見したらすぐに捕殺する
- ジャガイモの側にナス科やウリ科の植物は植えない(もし植える場合は、ジャガイモとの間にデントコーンやソルゴーなどを植えて壁にして飛来を防ぐ)
- 防虫ネットなどを使用し成虫の飛来を予防する
- 殺虫剤は対象の害虫だけに効果があるものを必要最低限で使用し益虫まで殺さないように注意する
ジャガイモの側にナスやウリ科の植物は植えないことが一番望ましいです。
植える際はデントコーンなどの植物を障壁として植えることで被害を防ぐことができます。
また畑が小さい場合などは防虫ネットなどが一番簡単で効果的です。
まとめ
テントウムシダマシは益虫であるナナホシテントウムシと異なりジャガイモやナスなどを好んで食害する害虫です。
見分け方は体が細かい毛におおわれていることや、成虫は動きが鈍いことなどがポイントです。
繁殖力がとても強いことからできるだけ卵の段階で駆除できるよう、普段から植物の葉裏など注意して観察しましょう。
また農薬を使用する際は、他の益虫を殺さない様に種類をよく選定してから使用することをおすすめします。