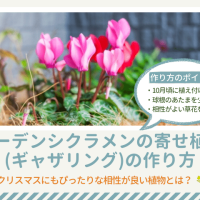- アデニウムの剪定について理解できる
- アデニウムの剪定が自分でできる
- アデニウムの剪定に必要な道具や準備・成功させるコツがわかる
- アデニウムの剪定に必要な道具や準備を行い成功させることができるようになる
アデニウムの剪定が気になっていても、やり方や意図が分からないと失敗しそうで躊躇してしまいますよね。アデニウムの剪定の目的や成功させるコツなどを、前もって分かっていればチャレンジしやすくなるはずです。
こちらの記事では、アデニウムの剪定方法と必要な道具や準備などを詳しく解説し、初心者でも剪定を成功させるコツを伝授します。
アデニウムの剪定を行う目的

アデニウムはキョウチクトウ科の落葉樹で、原生地では最大5mにもなるそうです。しかし日本の栽培下では樹高1m未満が多く、放置気味でも自然と樹形は整います。
では、アデニウムの剪定はどんな理由で行うのでしょうか。アデニウムの剪定には大きく分けて3つの目的があります。
- 不要枝の整理
- 枝数を増やす
- 幹を横に太らせる
アデニウムの剪定は「どういう樹形が理想なのか」により、やり方は多少変わります。どういうことなのか、次で詳しく見てみましょう。
不要枝の整理が目的
不要枝の整理は、大きくなり過ぎたアデニウムを、コンパクトに整理するために行います。一般的な樹木の剪定同様、傷んだ枝や込み入った枝を透かし、好みの高さで切り詰めましょう。
同時に根を整理すると、同じ鉢サイズのままで管理できます。自然樹形が好み(見た目の意匠性にはこだわらない)で、置き場所が限られているベランダ園芸などで行うと効果的です。
枝数を増やすのが目的
平凡な樹形から少し個性を出すため、一か所から枝が数本立ち上がる樹形にしたい場合にもアデニウムの枝の剪定を行います。
実生から剪定なしで育てていると、枝が幹からまばらに生え、すっと伸びて先端に葉が茂っている状態です。
このままでもスッキリした樹形なのですが、徒長した主幹や枝を切り詰めると、その切り口から新芽が生えて数本の枝が立ち上がるようになります。
こちらは、少しワイルドな風貌にしたい場合に行うので、好みの問題と言えるかもしれません。
幹を横に太らせるのが目的
更にマニア好みの樹形に育てたい場合「胴切り」を行うとよいでしょう。SNSや雑誌などで見かける「太ったモンスターのような体貌こそがアデニウムの理想の樹形!」という方は、2年苗ほどの小苗のうちに、思い切って主幹の途中からバッサリ剪定してみましょう。
時間はかかりますが、塊根植物らしいずんぐりとした姿に生長します。幹を横に太らせるには、胴切りの他に直根を切る「根切り」という方法もあるので、憧れの樹形に近付けるためには根切りも併せて行いましょう。
アデニウムの剪定に必要な道具・準備

アデニウムの剪定に必要な道具には、以下のものがあります。
- ナイフ(カッターなど)
- 癒合剤
- ティッシュ
- ナイフの消毒(バーナーやウイルス除去液など)
- 手袋
剪定前の準備には、
- ナイフの消毒
- 手袋の着用
などがあります。
塊根植物を複数鉢育てているならウィルス病を媒介させないよう、ナイフの消毒が必須です。ウィルス病は不治の病。罹ったら治ることはなく、廃棄処分しかありませんので注意しましょう。
画像右上の黄色い液体は、ウィルス除去の第三リン酸ナトリウム液です。刃を付けてからカットします。
また、アデニウムは樹液が皮膚に付くとかぶれるので、指先を動かしやすいよう手にフィットする手袋を着用してから剪定すると安心です。
アデニウムの剪定方法
アデニウムの剪定は水やりをしてから1週間ほど乾かし、体に張りのあるコンディションの良い株を使用します。剪定方法は以下の手順で行いましょう。
- アデニウムの枝を切る
- 樹液をティッシュで拭きとる
- 癒合剤を塗る
やり方を詳しく見てみましょう。
①アデニウムの枝を切る

混みあった枝や、徒長した主幹、枝をたくさん出させたい場所を見極め、切りたい場所から少し上をナイフでカットします。
少し上で切ることにより、幹枯れしてきた時の保険になります。枯れてきても程よい位置で止まってくれるでしょう。
②樹液をティッシュで拭きとる
アデニウムは幹や枝にしっかり水分をため込んでいるので、切り口からは緑色の樹液があふれてきます。樹液が収まるまでティッシュで軽く押さえましょう。
この樹液は皮膚に付くとかぶれることがあるので、手袋を着用。気を付けて行ってくださいね。
③癒合剤を塗る
樹液が大体止まったら、切り口に「トップジンMペースト」などの癒合剤を塗ります。癒合剤の役割は、雑菌の侵入を防ぐと同時に、傷口にフタをして体内の水分や栄養を逃さず、植物が弱るのを防ぎます。
アデニウムの剪定を成功させるコツ

「アデニウムを素敵な樹形に!」と期待が高まるのと同時に「失敗したらどうしよう?」と不安な気持ちになりますよね。枯らせてしまったらがっかりしてしまいます。アデニウムを上手に剪定するコツは何かあるのでしょうか。
剪定を行う時期
剪定の時期を誤ると、葉が枯れて樹勢が弱ってしまいます。そうならないためにも、剪定は夏の生長期に行います。最低気温20度以上で遅くとも7月中には終わらせましょう。
アデニウムは、強剪定しても芽吹く力が強い植物。いかにもキョウチクトウ科らしい性質を持っています。
ただし、新芽が芽吹くまでに1ヶ月かかるかもしれないので、特に寒冷地では、芽吹きが秋にずれ込まないよう逆算して剪定してください。
スパッと切る
アデニウムの枝や主幹はしっかりしているので、意外と堅く感じるもの。細い枝なら鉢に植わったままでも剪定できるのですが、太い主幹の剪定や、力の弱い女性などが手こずると、新芽が取れ切り口がボロボロになってしまうことも…。
それなら鉢から根ごと抜いて、野菜を切る時のような要領で剪定したほうが、力が入りやすくスパッと切れます。同時に植え替えを済ませてしまうとよいでしょう。
株が傷まないよう、なるべく時間をかけずにきれいにカットすることをおすすめします。
剪定後の育て方
剪定後は、しばらく明るい日陰で養生します。傷口が早く乾くよう、風通しの良い場所で管理しましょう。剪定する前に、週間天気予報を調べ、剪定当日から2~3日雨が降らないような日程で行うのがベストです。
梅雨時は雨が当たらないよう注意し、屋根のある場所で管理してくださいね。水やりは剪定から3日後から。葉が減った分、水の吸い上げが悪くなっているので、10日に1回くらいのペースから始めて様子を見てください。
まとめ
アデニウムの剪定方法についてまとめてみました。
アデニウムの剪定に必要な道具や準備・成功させるコツを事前に勉強しておけば、スムーズに剪定することができます。
丁寧かつ短時間で終わらせられれば、株の傷みも最小限に抑えられますよ。憧れのアデニウムの樹形を目指して頑張りましょう!